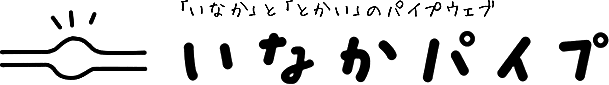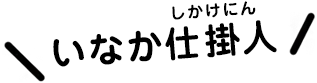株式会社御祓川
代表取締役 森山 奈美

受入事業者の資金で成果を出すインターンシップ
取組紹介
マチ・ヒト・ミセを育てる
株式会社御祓川は、自然循環を目的とした御祓川の浄化やまちづくり企画立案やそのサポートを通じた「マチを育てること」、地域人材循環を目的としたイベント企画運営・サポートやインターンコーディネネートを通じた「ヒトを育てること」、地域経済循環を目的とした「出店プロデュース」「能登の商品開発」を通じた「ミセを育てること」の3つが大きな取り組みです。その活動をより円滑に進める為に、体験型観光や地元料理教室等のプログムを用意する「うまみん」、販売ノウハウや売り場を提供する「能登スタイルストア」、新しいプロジェクトの担い手を呼び込む「能登留学」といったサービスで、地元の人の問題を解決する為のプラットフォームを提供しています。地域で暮らす・働く人と能登の場所・物との関係を再生させるというヴィジョンを持っています。

長期実践型インターンシップ「能登留学」
能登半島地震をきっかけに、復興について能登のまちづくりに携わる人々が話し合う中で多く聞かれたのが「若者がいない」という声。これまでも「仕事がないので若者が帰ってこない」という状況も長年指摘されてきたことから、2010年より国の事業を活用しつつ長期実践型インターンシップ「能登留学」を実施し始めました。
大学生を中心とする若者が、能登の事業者の下で、最低3ヶ月~1年間インターンシップをする研修プログラムです。研修プログラムとして、若者の成長はもちろんのこと、地元企業や地域の新しい挑戦や、企業課題や地域課題の解決につながるようなプロジェクトを設計し、インターンと受け入れ事業者が共に取り組んで、成果を出していくという長期実践型のインターンシップです。
能登移住へのきっかけづくり
地元にいる人だけでなく能登の外からやってくる人たちにも開かれた場を提供し、移住へのきっかけ作りも応援しています。さまざまテーマでお酒を交えて交流するイベント「まちづくりdrinks」では、この土地で何かをしたいと意気込む人同士がマッチングを助けています。これは地元の人・外からの人同士もあれば、地元の人同士のマッチングにもなっています。このイベントの参加者が能登に移り住んだという例も少なくありません。また始めたいことができた時には、クラウドファンディングでの資金調達支援や、活動拠点としてのシェアオフィスの提供などの非資金的なサポートを行っています。

ココがスゴイ!
事業者のビジネス課題の解決と担い手不足という地域課題を同時に解決!
インターンが取り組むプロジェクトが、受け入れ事業者のビジネス課題の解決につなげ、成果に結びつくという価値を生むことで、コーディネート料という対価を事業者から支払ってもらい、行政に頼らない持続可能なビジネスモデルを実現させています。
さらに、2010年度の第1期生4名の受け入れから始まり、2012年度までに40名以上の若者をコーディネートし受け入れ、2名が能登へ移住し、能登の課題を解決するための事業を起業しています。
このように能登留学の取り組みが、地元事業者の課題解決と、若者がいないという地域全体の課題解決につながっています。
人材を集める為の定置網モデル!
魚を奥へ追いやるように、観光で訪れた人たちや、能登留学を通して出会った若者を[短期滞在→移住→地域コーディネーター]へと段階的に育てていくという考え方のモデルを、七尾の定置網漁にちなんで「人材の定置網モデル」と呼んでいます。このような考え方を持って、能登へ訪れる人を捉え、その段階にあわせて関わり方を変えていく方法をとっています。
困りごと
移住者を地域の”担い手”化させる
定置網型モデルのように、どうにかして能登に移住した人を、地域を盛り上げてくれるような地域イノベーターあるいは、次の”担い手”として移住者を育てていきたいと考えています。しかし、移住ステージと担い手ステージには大きな差があります。その差を埋めていくためにも、定置網モデルでいう「奥へ、奥へ」と追いやっていく、ステップづくりを今既に住んでいる人と一緒に考えていかなければいけません。
何かしたくて移住した人が、それをするために1、2年も掛けて地域のネットワークを自分1人で作るのでなく、そういう人をサポートして、効率的に地域の中で事業展開できるような仕組みつくりたい。
移住するための”トリガー”づくり
移住者から担い手へという取り組みと平行して、よそ者から移住者へというステップアップも課題です。能登に興味を持ってくれ、移住したいと思う人はプラットフォームを通じてかなり増えてきています。しかし、そういった人たちが移住を決断する為に、こちら側から「来なよ」と言える最後の一手(トリガー)がまだ弱く、狭い範囲でしかできていない。
例えば、株式会社御祓川で、雇用がつくれ、求人も出せるので「来なよ」といえる条件を提供することができますが、それは自分たちの範囲だけであって、能登全体として同時多発的にできるかと言われればその体制はまだ整っていません。今後は、能登全体で広範囲に提供できる移住決断のための”トリガー”づくりがこれまで以上に求められています。
本ページは、平成25年度 地域をフィールドとした産業人材受入のための環境整備のあり方に関する調査事業(実施:四国経済産業局)において調査した時点のデータを活用して作成したものです。